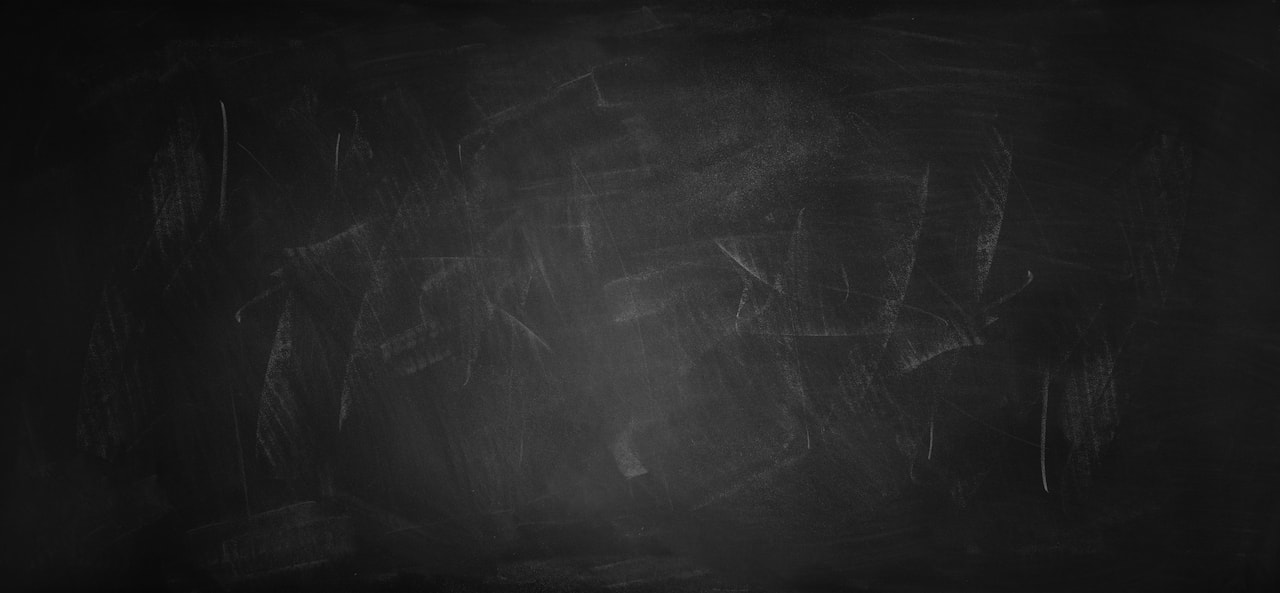\ 無料で体験できます /

「模試では数学も英語も時間が余るのに、国語だけ毎回ギリギリ」「解き終わらずにマーク欄が半分空白のまま提出した」そんな声があとを絶ちません。
長年入試対策を指導してきた経験上、国語の時間不足は決して特殊な悩みではなく、むしろ多くの受験生がつまずく“共通ポイント”です。
特に近年は文章量の増加や記述配点の拡大が顕著で、読解スピードと処理能力の差が得点差へ直結しています。
しかし、「自分は読むのが遅いから無理」と諦める必要はありません。
国語は「読み方」と「解き方」を変えるだけで、同じ読解力でも得点効率が大幅に上がる科目だからです。
例えば、設問を先に読む「目的読み」だけで平均6分短縮、段落要点の「拾い読み」が身につくとさらに4〜5分短縮できたという実例も珍しくありません。
この記事では時間が足りなくなる原因と時短テクニック、練習方法を具体例と経験談を交えながら徹底的に解説します。
読み終わるころには「試験時間が足りない」という不安が「次の模試が楽しみ!」に変わるはずです。
モコスタ統括マネージャー
小澤 珠美

大学卒業後、大手進学塾で高校受験・中学受験の指導に15年間従事。特に中学受験において、御三家中学をはじめとする超難関校の算数指導・受験対策・保護者のサポートに尽力し、合格実績に貢献。
その後独立してさらなる成果を出し続けモコスタ専属の指導者となる。これまでに蓄積したすべてのノウハウを投入し、モコスタに通う受験生全員の第一志望校合格を全力でサポートする。
著書:『中学受験超成功法「ママは楽しく息を抜く」』ギャラクシーブックス 2017年
共著:『未来を創る〜私たちが選んだ道〜 輝く女性起業家』ブレインワークス 2017年
\近くの教室でお待ちしています/
なぜ国語だけ時間が足りない?3つの原因を解説
大きく分けて、「文書量の多さ」「問題形式の多様さ」「読み方と解き方の戦略不足」が原因として考えられます。
文章量の多さ
国語の長文は1段落あたり平均230〜260字。
4段落構成でも約1,000字、二題出れば2,000字超。英語長文よりも実は目を通す純粋な文字数が多いといえます。
また、算数などとは異なり、本文を読み切ったあとに設問文を精読し、選択肢を比較することの繰り返しになるため、「問題文を一度読めばOK」と言えないのが国語の特徴です。
つまり、単純な文章量も、設問を解くうえでの識字量も多いと言えます。
問題形式の多様さ
また、問題形式が多いのも国語の特徴。
現代文・古文・漢字・語句整序・記述など、設問によって問われる能力や試行プロセスが異なるため、瞬時に思考のギアチェンジをする必要が生じます。
読み方と解き方の戦略不足
「全文を精読できれば正解率がアップする」と考える生徒は多くいますが、実はそうではありません。
長い文章中において解答の根拠になる部分(核となる部分)は全体の40%~50%ほどと考えていただいて大丈夫です。
そして、配点を意識しながら解く戦略も重要です。
時間との勝負になるため、コストパフォーマンスの良い問題に取り組むことも一つの作戦。
「少ない配点問題に時間をかけすぎた」という生徒を数多く見てきているので、要注意です。
時間を節約するための5つのテクニック
時間が足りないというお子さんのために、具体的なテクニックを教えます。
すべてのテクニックが誰にでも当てはまるわけではないので、性格や苦手分野に合わせた取捨選択をしてみてくださいね。
設問先読みで「目的読み」を意識する
本文を開く前に、まず設問をざっと眺めてください。
登場人物や筆者の主張、具体例など問われている内容をメモしてから本文に戻ると、視線が自然に答えの手がかりへ向かいます。
読み進めながら「ここが根拠だ」と印を付けるクセをつければ、平均で3〜4分は短縮できます。
過去問演習では設問に付箋を貼り、対応段落を見つけしだい解答する逆走トレーニングを取り入れると効果がはっきり感じられるはずです。
段落ごとの要点読みを意識する
長文のすべてを丁寧に読む必要はありません。
「段落の冒頭文には主張が、末文にはまとめが、そして逆接のあとの一文には筆者の本音が現れやすい」まずはそこを押さえましょう。
具体例の部分は斜め読みで十分です。
最初は不安でも、テスト形式の演習で正答率が落ちないことを確認すれば全部を読まない勇気が身につきます。
「選択肢から読む」解き方も有効
マーク式の問題では、選択肢を先に読んでキーワードを拾い、その語句が現れる段落だけを精読すると時間を大きく節約できます。
極端な表現や論点のすり替えといったひっかけの定番パターンを覚えておくと、誤答を一瞬で除外できるようになります。
模試が終わったら、誤答を導くキーワードをリスト化し、次回は見た瞬間に切り捨てられるか試してみてください。
記述にかける時間を決めておく
記述問題は「構想・執筆・見直し」を合計5分以内に収めると決めておくと、ほかの設問に割く時間を守れます。
「要素を二つ以上盛り込み、接続語で論理をつなぎ、主語をぶらさない」この3点を満たせば部分点は十分に獲得可能です。
制限時間を過ぎたら書き途中でもいったん切り上げ、マーク欄や残りの選択肢へ移動する損切りの意識が総合得点を引き上げます。
古文はキーワードを手がかりに拾い読み
古文は全文を訳す必要はありません。
設問や選択肢から人物・心情・場面を示す語句を探し、その周辺だけを丁寧に読めば十分対応できます。
係り結びの結論部に目印を付けると答えに直行でき、頻出語をカードで覚えておけば意味推測のスピードも上がります。
「ぞ・なむ(なん)・こそ」は強意(特に訳す必要なし)、「や・か」は疑問または反語の意味(必ず訳す)を表すことを知っておきましょう。
時間内に解ききるための勉強法|スピードと精度を同時に上げる
速読ではなくスキミング読みを練習する
スキミング読みとは、流し読み・すくい読みと呼ばれる読み方です。
練習の仕方としては、毎朝新聞のコラムから30秒で要旨を抜き出し、根拠を2行メモするトレーニングを続けると視線移動が素早くなります。
「読んだあとは段落ごとに8字以内の見出しを自作し、本文を確認して修正する」この往復で要旨抽出の精度も上がります。
選択肢の「消去法」をパターン化する
過去3年分の模試を振り返り、誤答となる選択肢に共通する言い回しをノートにまとめておきましょう。
極端な語や逆接無視など典型的な誤りは何度も登場するので、30秒で判断を下す練習を週に数回行うと瞬発力が鍛えられます。
記述は型を覚える+テンプレ練習
「筆者の主張は○○であり、その理由は△△と□□である」というように、よく使う構文を五パターンほど暗記しておくと、ゼロから文章を組み立てる手間が省けます。
良質な模範解答を声に出して読み、要素をマーキングしたうえで書き写すと語彙とリズムが身体に染み込み、執筆スピードが倍増します。
過去問・模試の振り返りを「時間軸」で記録する
問題冊子の余白に設問ごとのラップタイムを書き、解き終わったら合計時間を確認して表にまとめましょう。
週ごとに棒グラフにすると改善の度合いが一目で分かり、学習のモチベーションも保ちやすくなります。
時間不足で失点しないためのマインドセットと注意点
まず意識したいのは「完答より完走」です。
高得点者はすべての問題に正解しているわけではなく、手を付けた問題の正答率が高いのです。
配点が低い長文設問や、自信が2割以下の問題は思い切って後回しにしましょう。
特に記述は字数が多いと配点も高いように見えますが、採点は部分点中心です。
要素を2つ盛り込んで六割取れれば十分と割り切るほうが、全体の得点を守れます。
最後の5分は得点を守る時間だと考えてください。マーク位置のずれは0点に直結します。
解答欄をすべて指差し確認し、記述の誤字脱字をチェックする習慣が、最終的な失点を大きく減らします。
まとめ
国語で時間が足りなくなる原因は、読解スピードではなく戦略の欠如です。
「設問先読みで目的を定め、段落の要点だけを拾い、記述の時間をきっちり区切り、古文はキーワードで拾い読みする」これらを徹底すれば、同じ読解力でも解答にかかる時間は大幅に短縮できます。
さらに、スキミング読み、誤答パターンの消去法、記述テンプレの活用、ラップタイムの記録という四つの訓練ループを日常学習に組み込めば、スピードと精度を同時に高められます。
最後に過去問を本番時間で解き、タイムと正答率を分析するサイクルを繰り返せば、自分に合ったペース配分が定着し、本番でも落ち着いて得点を積み上げられるはずです。
完璧主義を手放し、必要な情報だけに集中する選択と集中の姿勢さえ身につければ、国語は「時間が足りない科目」ではなく「安定して得点を稼げる科目」へと変わります。
今日から試して、次の模試で効果を確かめてみてください。
モコスタとは?
モコスタは、経験と実績豊富な講師が中心となり学習指導を行う学習塾です。
補習を中心とした個別指導から、小学1年生から6年生までの本格的な集団指導まで、受験合格に向けたサポートを行います。
| コース/クラス名 | 概要 |
|---|---|
| ベーシック | 小学1年生から中学3年生の補習クラス。学校の授業・受験勉強の補習を行います。 |
| マンツーマン | 小学1年生から中学3年生の完全マンツーマンクラス。学習塾の予習・補習や、苦手科目の重点的な学習を行います。 |
| アドバンスクラス | 小学1年生と2年生を対象に、楽しく学習しながらも主体的に学ぶことを重視している集団指導クラスです。 |
| 中学受験クラス | 小学3年生から6年生を対象に、本格的な受験対策を行う集団指導クラスです。 |
個別相談と無料体験会を開催しています
モコスタでは、随時「個別相談」と「無料体験会」を開催しています。
ご相談内容にあわせて、経験豊富な講師陣が丁寧に対応させていただきます。
- 塾の雰囲気を見てみたい
- どんな指導をしているのか教えて欲しい
- 講師に受験に関する相談をしてみたい
どんなご相談でも、お気軽にお申し込みください。