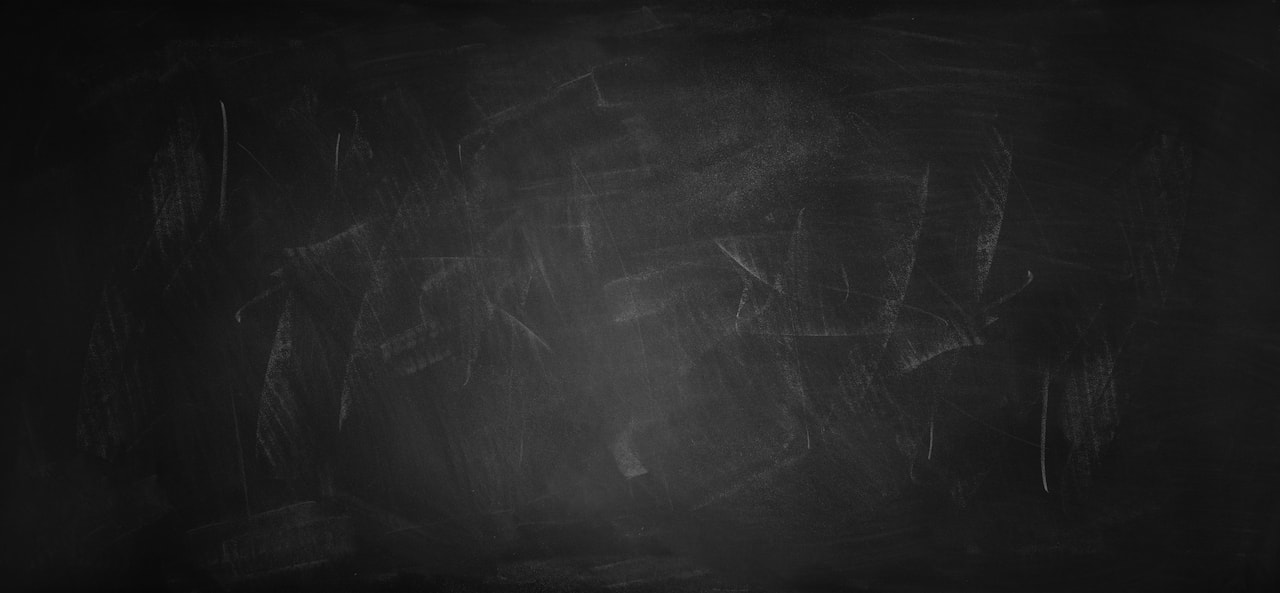\ 無料で体験できます /
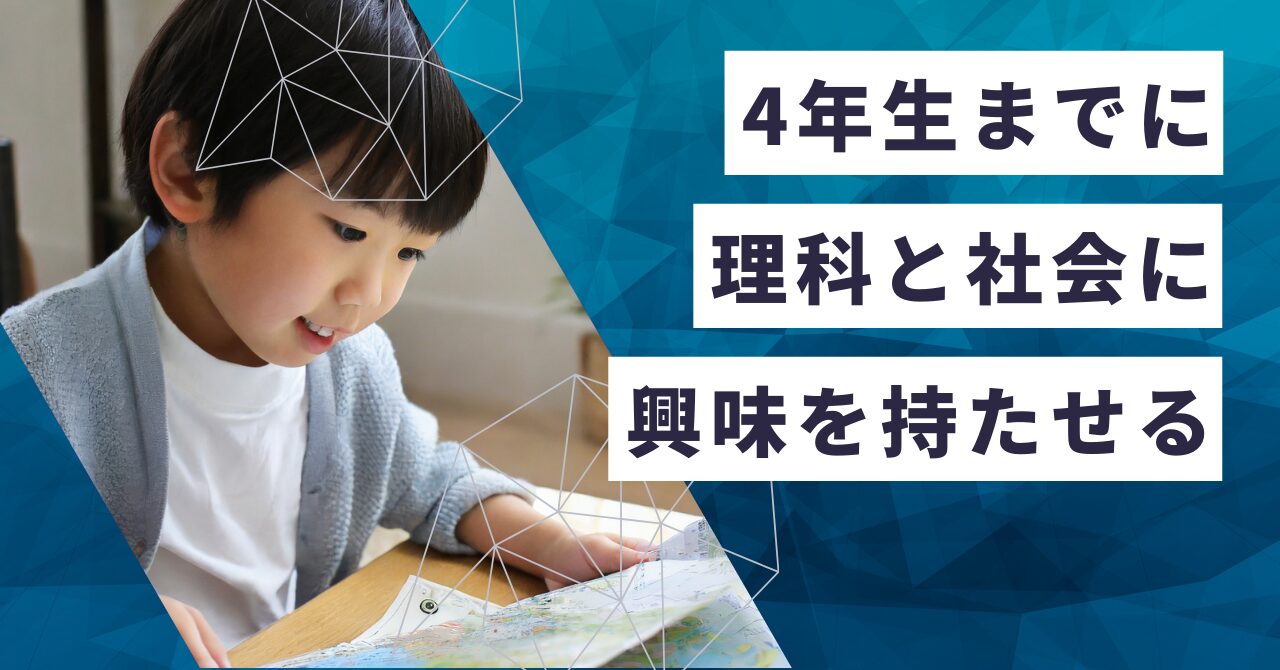
中学受験を目指すにあたって、理科や社会をどうやって勉強させようか迷っているご家庭も多いでしょう。
そこで今回は、理科・社会に対する興味関心を高めるべくご家庭ですべきことを解説していきます。
モコスタ統括マネージャー
小澤 珠美

大学卒業後、大手進学塾で高校受験・中学受験の指導に15年間従事。特に中学受験において、御三家中学をはじめとする超難関校の算数指導・受験対策・保護者のサポートに尽力し、合格実績に貢献。
その後独立してさらなる成果を出し続けモコスタ専属の指導者となる。これまでに蓄積したすべてのノウハウを投入し、モコスタに通う受験生全員の第一志望校合格を全力でサポートする。
著書:『中学受験超成功法「ママは楽しく息を抜く」』ギャラクシーブックス 2017年
共著:『未来を創る〜私たちが選んだ道〜 輝く女性起業家』ブレインワークス 2017年
\近くの教室でお待ちしています/
4年生までに理科と社会に興味を持たせる方法
中学受験を目指すにあたって、お子さんが頭に入れなければならない理科・社会の知識量は、結構なボリュームになります。
「理科・社会は暗記科目ではない」とはよく言われることです。しかし、思考したり、分析したり、表現したりするためには、その土台となる知識が身についていなければ、話になりません。
理科的分野・社会科的分野に対する興味関心は、3年生までに(本格的な受験勉強がスタートするまでの間に)、ぜひ、お子さんに持たせていただきたいな、というふうに思います。
4年生、5年生と学年が進むにつれて、覚えなければならない内容は、非常に多くなっていきます。だからこそ、3年生までの間に、「理科は楽しいな、社会は面白いな」といった感覚を、是非、お子さんに身につけていただきたいのです。
小さい頃からの生活習慣は、ひじょうに大切です。低学年のうちから、受験勉強一色に染め上げるのではなく、たとえば、動物園や水族館など、いろいろなところへ連れていく。あるいは、図鑑や地図を一緒にながめてみる。テレビのニュースなどをネタに、お子さんを会話を交わす……。
今でいえば、「ウクライナ戦争」のことが毎日、報道されています。では、ウクライナという国はどこにあるのか? ロシアはどんな国なのか? ウクライナの国旗(青と黄色の二色旗)には、どんな思いが込められているのか?……等々。
そんな切り口から、お子さんの好奇心を育んでいく。こうした感覚が、当たり前のように身についていると、4年生・5年生からの理社の勉強にも、スムーズに乗っていけると思います。
では、今3年生の子のいる我が家で、手軽に始められることはないだろうか? そう、お考えになる方もいらっしゃるでしょう。
もちろん、今までに、さまざまな準備がなされていれば、それに越したことはありません。ですが、これから残り半年足らずの時間で、少しでもお子さんの好奇心を育てていけるような、何か簡便な方法はないでしょうか?
机に向かわず地理に興味を持つ
たとえば、こんなのはいかがでしょう。「目指せ!日本地図博士」
地理を学ぶのに、机に向かう必然性はありません。リビングやお風呂場に地図を貼っておく。あるいはちょっとしたパズルとか、パーツになっているようなものとかもありますよね。そういったアイテムを利用しながら、ゲーム感覚でお子さんと一緒に楽しむ。
目標は、そうですね、4年生になるまでに、「1都1道2府43県」の位置と名前をしっかり覚える、というところでしょうか。これだけで、4年生の社会(ひいては理科)の学習は、ぐっと楽になるでしょう。
さらに余力があるのであれば、「都道府県のかたち」(パズル感覚で楽しめるゲームが、ネット上にもたくさんありますよ)や、「各都道府県の“ふるさと自慢”」(「みかん」だったら、和歌山・愛媛。「りんご」だったら、青森・長野……)まで、手を広げられるといいと思います。
さきほど、リビングやお風呂に地図を貼っておく、という話をしました。ささいなことかもしれませんが、ここから生まれるメリットは、かなり大きいと思います。「勉強勉強していない」というのもいいですね。
テレビのすぐそばに地図がれば、ニュースでも、バラエティでも、あるいはドラマでも、ちょっと気になる地名や場所がでてきたときに、「これってどこかな」なんて、話をふってみる。そんなところから、地図に対するお子さんの興味が高まれば、一家団欒にもなりますし、一石二鳥ですよね。
仮に、お子さんが、「どこだか分からない、そんなの知らない」と言っても、怒るのは、NG。まずは、楽しく学ぶ。地図に慣れ親しむ。そんな感覚を大切にしてもらいたいと思います。
今日からご家庭に一枚、日本地図でも世界地図でも、貼ってみられてはどうでしょうか?
モコスタ統括マネージャー
小澤 珠美

大学卒業後、大手進学塾で高校受験・中学受験の指導に15年間従事。特に中学受験において、御三家中学をはじめとする超難関校の算数指導・受験対策・保護者のサポートに尽力し、合格実績に貢献。
その後独立してさらなる成果を出し続けモコスタ専属の指導者となる。これまでに蓄積したすべてのノウハウを投入し、モコスタに通う受験生全員の第一志望校合格を全力でサポートする。
著書:『中学受験超成功法「ママは楽しく息を抜く」』ギャラクシーブックス 2017年
共著:『未来を創る〜私たちが選んだ道〜 輝く女性起業家』ブレインワークス 2017年
\近くの教室でお待ちしています/